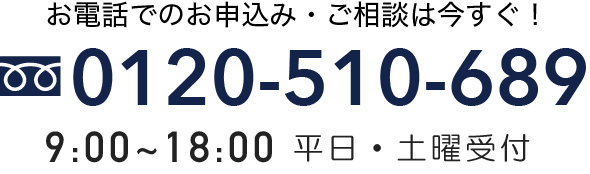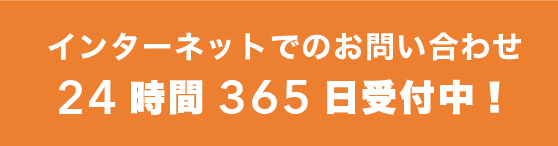二度とカビを見たくない!!防カビ対策5つの方法


市販のカビ取り剤でカビを除去してもまたすぐ生えてくる・・・なんか健康被害も心配だし、なによりも黒カビがある中で生活したくない!!そんなお悩みの方にカビ対策のプロが教える、5つの防カビ対策方法についてご説明します。
[toc]1.こまめな掃除で栄養を断つ
カビが生えるための条件の一つが「カビのえさがあること」というのがあります。
えっ、カビって餌を食べるの!!と思いましたか? 実はカビは埃、垢、ダニの死骸、石鹸カス、皮脂などを栄養源として成長するのです。 逆に言ってしまえば、栄養源を断ってしまえば、カビにとってそこはとても生えにくい環境になります。
1―1.壁や床、天井の垢やホコリの除去
壁や床、天井のカビの栄養源は人間の垢や堆積した埃です。
それらを溜めないことが防カビ対策としてはとても有効なのです。
そのためには、多少面倒ではありますが、クイックルワイパーやタオルを使って、ホコリをさらうように小まめに軽く水拭きをしましょう。
特に天井はかなり面倒だと思うので、週に1~2回クイックルワイパーを逆さにして掃除してあげましょう。アルコール拭きだとなお良いです。
しかし、天井や壁が珪藻土など拭くとボロボロと取れる素材の場合は、静電気で埃をキャッチするモップで軽く拭いてあげるだけでも大丈夫です。
1-2.寝具のダニ除去
寝具の内部にはカビの餌となるダニが数多くいます。
寝具の内部にカビ菌が増殖すると、咳や喘息、肺炎などの健康被害を悪化させる原因になります。
また、ダニはカビの原因となり健康被害を引き起こすだけでなくダニそのものがアレルゲン物質ですので、確実に除去した方がよいです。
しかし厄介なことに、ダニはなかなか取り除くことができません。
天日干しをしても裏側へ移動してしまうし、布団をたたいても生きているダニはしがみついて取れません。
レ○コップのような商品も実際はダニを殺す効果は薄いと言われていますし、なかなか対策が難しいのが現状です。
手間暇をかけるとするならば、布団乾燥機の中に入れて熱した後の布団に掃除機を当ててまんべんなく吸い取る。ここまでやればだいぶ改善するかと思います。
当社では、布団のダニ除去のサービスもしていますので、気になる方は一度当社までご相談ください。
1―3.浴室の石鹸カスや皮脂の除去
浴室のカビの栄養源は壁や天井に付着した石鹸カスや皮脂などです。
つまり、それらを常に取り除いておけば、カビが繁殖しにくいお風呂になるということです。
具体的には、入浴後に風呂の壁や天井を全てできるだけ熱いお湯で流してください。
※やけどに注意してください。
これにより①皮脂や石鹸カスが解けて流れる②カビ菌が熱により弱ります。
その後冷水で再度流し、ふき取ることにより、温度と湿度の環境も整います。
1―4.エアコン内のホコリの除去
エアコンの中はカビの宝庫です。
なぜかというと、湿度、温度もさることながら、カビの餌であるホコリがフィルターやその他内部にびっしりだからです。
ですので、小まめにフィルター掃除をした方が、空量の効率も上がるだけでなく、エアコン内部でのカビの繁殖も防ぐことができます。
少なくとも年に一回、可能であれば梅雨前と冬前の二回は業者に頼んで内部洗浄してもらうことをお勧めします。
2.湿度を下げる
カビ菌には様々な種類が存在し、それぞれ「好みの湿度」というのが違います。
そのほとんどが、湿度が高い環境を好みます。 以下は、代表的なカビの【湿度(横軸)】と【生えてくるまでにかかる日数(縦軸)】の関係です。 (横軸の0.8という数字は、湿度80%という意味です。)
たとえば、クモノスカビは湿度90%では10~20日くらいで生えてきますが、湿度を85%に下げると、60日~70日立たないと生えてこないことがわかります。
このように、カビを生やさない対策として湿度対策はとっても重要なのです。
「どうしてもカビが生えてきてしまう」という方は、まずは以下の湿気対策に力を入れてみてはいかがですか?
2―1.リビングの湿度対策
室内の壁紙や天井にカビを生やさないためには、その部屋の湿度を下げてあげることが有効です。
具体的に効果的な方法は除湿と換気と結露対策(③を参照)です。 除湿はできれば除湿器を使用してください。市販の湿気を吸い取る除湿剤などは、タンスなどの密閉空間であればまだいいですが、なかなか部屋全体に効果が行きわたらず、結局部屋の隅の空気の湿度は変わらないことが多いのでお勧めできません。
換気は窓を開ける、換気扇を回す、サーキュレーターを回すなどでとにかく空気を動かしてください。特に湿気というのは天井近くの隅にたまりやすいので、サーキュレータを回す場合は上向きで回すと良いでしょう。
2―2.寝室内の除湿
防カビのための湿度対策で一番難しいのがこの寝室です。
カビ対策のみを考えれば、除湿をするのが好ましいのですが、あまり睡眠中に乾燥させるとのどを傷めたり、風邪を引いたりする原因にもなります。 ですので、とにかく空気を循環させて、湿気をためないことにより注意して頂いた方がよいでしょう。
天井に向けて扇風機を回しておくと、湿気がたまらないだけでなく直接扇風機の風を当てずに体感温度が下がるので梅雨や夏は快適です。
2―3.浴室内の湿度対策
浴室の湿度対策は、お風呂を上がるときの一手間がとっても重要です。
上がる前になるべく水滴を壁や床に残さないように水を切ったり乾拭きしたりした後、24時間換気をするようにしましょう。
浴室乾燥機がついているのであれば上がった直後は1時間ほど乾燥→24時間換気がベストです。
もし乾拭きが面倒だ、というのであれば、水はけがよくなる親水性のガラスコーティングなどを壁や床に施しておくと、水滴がたまらずお勧めです。
3.結露対策
もしもあなたの家のカビが窓際や北側の壁面に生えていたとしたら、それは結露が原因かもしれません。結露が起こると壁紙や窓枠が湿るのでカビにとって絶好の環境になってしまうことが多いです。
結露の原因は、窓や日の当たらない壁面の温度と室内の空気の温度とで温度差が生じると、窓や壁に空気が急に冷やされて、その面に結露が生じます。
結露を放置してしまうと、窓枠やパッキン、そしてカーテンなどが常に湿った状態になってしまい、カビが非常に発生しやすい環境になります。
具体的な対策としては
1.小まめに拭く、
2.室内を除湿する、
3.二重ガラスや断熱コーティングにより温度差をなくす
の三つがあげられます。
3の二重ガラスや断熱コーテイングにより温度差をなくす、に関しては別記事「最新技術で結露を防ぐ」を参照してください。
4.家具などの配置の対策
いくら室内に除湿器をおいたりしていても、家具を壁際にべったりとおいてしまうと背面に空気がたまってしまいます。
また、掃除も小まめにやることが難しくなってしまうので、カビのえさとなるホコリもたまりやすくなってしまいます。
タンスや本棚は壁から少し隙間を開けて置き、たまに後ろを長い棒のついた掃除道具でホコリ掃除をしてあげると良いでしょう。
扇風機やエアコンの空気が壁と家具の隙間に流れ込むように配置するのもとても効果的です。
可能であれば、下にすのこなどを敷いて、床と家具の間に隙間を作るとベストです。
また、押し入れやクローゼットも同様で物を詰めすぎないように注意しましょう
5.カビを根こそぎ取る
カビを二度とはやさないためには、一度カビ菌を根絶やしにする必要があります。
除カビが中途半端だと再発の確率は大幅に上がってしまうため、除カビは徹底的にやることで、その後の防カビの対策にもなります
ココでの注意点は「見た目がキレイになったからといって満足しないこと」です。
カビという生き物はそもそも透明な菌で、我々の目には見えません。我々が普段見ている黒や緑のカビは、実は菌糸や胞子の部分なのです。
しかし、除カビしてきれいになったように見えても実は菌核と呼ばれるカビの本体というのは、なかなか殺せていないことが多いです。
タンポポに例えると、綿毛の部分だけが人間の目に見えているので、タンポポの綿毛だけを刈り取ってしまえば根や葉や茎は残った状態でもきれいになったように見えてしまいます。しかし、このような中途半端な除カビを行っても、根は生きているので、また数日で再発してしまいます。
とにかく、カビを根っこから分解して根絶やしにするためには「見た目がキレイになる」という程度の対策は絶対にNGです。
5―1.自分でカビを取る場合
市販のカビ取り剤や漂白剤でカビを取る場合に気を付けて頂きたいのが、「時間」です。
市販のカビ取り剤というのはそこまで強く作られていないため、時間をかけてカビを分解していたなくてはいけません。最低で30分、可能であれば1~2時間はおいてください。
特に、見た目にはすぐに漂白されてきれいになったように見えてしまうので、そこで安心しないように注意です。
また、壁面やパッキンのカビを取るときはカビ取り剤が流れたり蒸発したりしてカビの上にとどまってくれないので、キッチンペーパーやラップを使って湿布しましょう。(詳しくは家庭でもできる、プロのカビ取り専門業者が使うカビ取りのテクニック記事を参照)
5―2業者に頼んでカビを取る場合
カビを業者に取ってもらう場合は、できればハウスクリーニングや便利屋さんではなく専門知識を持ったカビ取り業者を選ぶべきです。
なぜなら、ここまでお読みいただいた対策方法を普通の掃除屋さんでも知らない人が非常に多いからです。彼らの多くは掃除のプロですがカビに関する知識は一般方々とそこまで変わらないのが正直なところです。
二度とカビを生やさないためには、この「根こそぎ取る」という作業がとても重要になるため、中途半端な除カビ施工は再発の可能性を大幅に上げてしまうので要注意です。
5―3.リフォームする場合
壁紙や床の剥がれ、その裏側のコンクリートのカビなどが見られた場合は、リフォームすることをお勧めいたします。
ここに大きな大きな落とし穴が待っています。
ハウスクリーニング業者がカビについて意外と知らないように、リフォーム屋さんもカビの対策については素人さんが多いです。
彼らは見た目を非常に重視するので、こんなことを平気でやってきます。
「カビが生えてきたから上からペンキを塗りましょう」
「コンクリートにカビが生えてるから、壁紙で隠しましょう」
以下の写真は以前カビ取りを行ったサロンの写真です。塗装の下にカビがいることがわかると思います。


こんなことをされてしまったらもう終わりです(詳しくはカビに困ったときの失敗しない業者の選び方記事を参照)
ペンキの中も壁紙の中もカビは侵食してすぐに表面に達します。その時に上から除カビ剤でカビ取りをしても遅いのです。
なぜなら、ペンキを塗り重ねたり壁紙を張ったりしてしまうともう除カビ剤は奥まで届かないからです。
何度も言っている通り、二度とカビを生やさないためには、一度根絶やしにしないといけませんから、ペンキを塗る前、壁紙を張る前にその奥の板やコンクリートをきちんと除カビしてあげる必要があります。これをしないと何をやってもカビが生える部屋が出来上がってしまいます。リフォームをする際は、カビ取り業者を呼んで、適切な処理を行うように注意してください。
6.まとめ
二度とカビを生やさないためには
①栄養を断つ
②湿度対策をする
③結露対策をする
④家具の配置を考える
⑤一度カビを根絶やしにする
の5つの方法を駆使すれば防カビ対策は完璧です!
ここまでやればかなりの確率であなたの家もカビが二度と生えなくなるはずです。
しかしここまでやってもダメ、もしくは労力がかかってなかなか対策できない、という方には最後の武器「防カビコーティング」が残されています。
詳細は以下の記事で。
防カビのコーティング一覧とその選び方
当社では、カビの知識を有する建築士×カビの研究員×カビ取り歴30年のカビ取り職人の連携により、他社では真似できないカビが生えない空間づくりをしております。
カビにお困りの際は、一度当社までご相談ください。