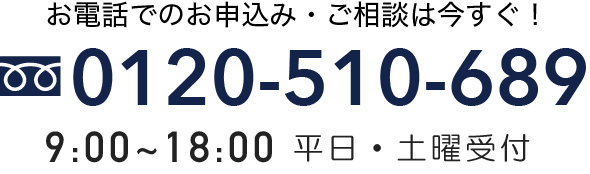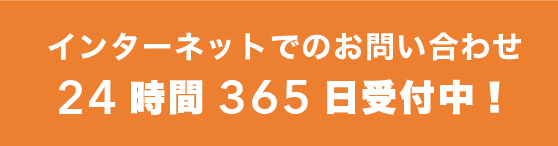カビ対策のプロが教える壁のカビ取りと防カビ方法


壁に生えたカビを見つけるとその部分が目立ってしまい気になってしまいます。
特に壁が白いとさらに目立ってしまいます。そんな時にすぐカビ取り業者にお願いするのもお金がかかるし、面倒ですよね。
ここでは我々カビ取り業者を呼ばずに自分でできるカビ取り方法をお伝えします。
[toc]
1.なぜ、カビが壁に生えるの?
壁に生える原因として3つあります。
(1)温度差による結露によってカビが生える
室内と外気の温度差が大きくなると外壁に面した壁に結露が発生する可能性があります。
(2)空気の滞留による湿度管理が悪いためカビが生える
空気が滞留する原因として、空気の流れの仕組みを知っておく必要があります。
風の流れは、やはり四隅が空気の流れが悪くなる可能性があります。そのため、四隅や天井と壁の境でカビが発生することが多いのです。
(3)漏水によりカビが生える
上階から何らかの理由により、水が落ちてくるケースか、自身の住宅で水道管の劣化や洗濯機の水が溢れることで、水が壁に吸収されカビが生えてくるケースです。
2.壁に生えたカビを放置するとどうなるの?
今まで、お客様のご自宅の特徴として、一部カビが生えてしまった箇所を放置した結果、2週間から2ヶ月程度で部屋全体にカビが広がってしまいお客様ご自身で対策できるレベルを超えてしまって依頼をいただくケースが多いです。
カビを放置すると、部屋の壁全体に広がるだけでなく徐々に奥まで進行していきます。すると最初は壁表面の壁紙だけだったカビが、その奥のボードや断熱材の内部まで進行してしまいます。
そのせいで、最初は表面を除カビだけすれば対処可能だったカビも、壁紙の交換が必要、ボードの交換が必要、断熱材の交換が必要と侵食されて行ってしまい、費用が高額になるケースがほとんどです。一度奥まで侵食してしまうと、安価で表面的な除カビ処理をしても菌が残ってしまうので再発率が跳ね上がるため、結局は高額の費用が掛かります。
そして、1番怖いのは、やはり健康を害することです。カビというのは今は大丈夫でも長い期間吸入し続けると体調を害してしまうケースが多いのです。カビを放置してしまったお客様の中には、肺炎になり入院された方や喘息を発症したお子様もいらっしゃいます。
以上のように室内の壁に生えたカビというのは放置してしまうと①業者に依頼しないと手に負えなくなるほど繁殖し、高額な費用が掛かる②長期でカビを吸入して健康を害する、といった事態が発生します。そうなる前に早期の段階でお客様ご自身の手で今すぐ除去することが費用面でも健康面でも非常に重要になってきます。
3.壁に生えたカビの取り方
ここからは壁に生えたカビをお客様の手で取るにはどうすればいいのか、どこまで行ったら業者に依頼したほうがいいのかを解説していきます。
3-1.壁紙【クロス】
壁のカビ取りの依頼で最も多いのが壁紙に生えたカビです。ここで注意しなくてはならないのが、一般的な市販のカビ取り剤は本当は壁紙には使用できないという点です。
市販のカビ取り剤のほとんどは次亜塩素酸ナトリウムと、水酸化ナトリウム(水酸化カリウムの場合もあり)が使用されています。このうち、次亜塩素酸ナトリウムは乾けば塩化ナトリウム(食塩)になりますが、水酸化ナトリウムは乾いても、再度水に溶けると強アルカリになります。
強アルカリは皮膚の表面を溶かす作用があります。つまり、市販のカビ取り剤をしみこませた壁紙は、乾いた後でも濡れた手で触ると皮膚の表面が溶けてしまうということです。
これが個人で壁紙に生えたカビ取りが難しい大きな原因です。なので、できれば市販のカビ取り剤は使用しない、どうしても使用する場合は大量の水をしみこませたスポンジやタオルで何度もふき取り、極力その箇所には触らないようにしましょう。さらに、業務用・市販問わず、カビ取り剤というのは漂白作用があるので壁紙に使用すると脱色してしまう可能性があります。
布クロスの場合退色してしまうことが多いのですがビニールクロスでも変色してしまう場合もあります。我々も様々な現場で壁紙を見ていますが市販のカビ取り剤よりも10倍以上強い業務用カビ取り剤を使っても脱色しない壁紙もあれば、かなり薄めても脱色してしまう場合もあるため、一概には言えません。目立たないところで一度脱色具合を試してみるのが一番確実かと思います。
カビ取り剤で試した結果、壁紙が漂白してしまった場合、カビ取り剤が使えないので、市販のアルコール除菌液で拭くことをお勧めします。この場合、アオカビや白カビなどの場合は拭いただけで落ちる場合もありますが、クロスに生えた黒カビ等の色はほぼ落ちませんのでご注意ください。
アルコールでの処置の場合再発の可能性が高いので、湿度を60%以下に保ち、こまめにアルコールでふくなどの対策をする必要が出てくるかと思います。それでも、面倒くさがらずにこまめに早期対処をしないとどんどん繁殖してしまいますので、根気強く対策してください。
カビ取り剤で試した結果壁紙が漂白しない場合、カビ取り剤を噴霧後、キッチンペーパーを上から当てて30分程放置してください。これで表面についたカビであれば、ある程度落ちると思います。落ちない場合は2回ほど同じ作業を繰り返すとほぼ完ぺきに落ちるはずです。
上記でも説明した通り、このまま放置するのは生活するうえでよくないので、水を含ませたスポンジやタオルで何度も拭きましょう。壁紙の中に残留した水酸化ナトリウムを水に溶かして吸い取るイメージで濡らして拭いてを繰り返すとよいかと思います。水分を残したままですと再度カビが発生する可能性がありますので、乾拭き後ドライヤー等で乾燥させればよいかと思います。
念のため施工個所はなるべく触らないほうが無難でしょう
これで落ちない場合や、うっすら影が残る場合、もしくは何度やってもすぐ再発する場合は、壁紙の裏側までカビが生えている可能性が高いです。ここがお客様ご自身で対処可能なカビと、業者を呼ぶべきカビのラインです。
なぜなら一般的なビニールクロスというのは、中に防水シートが入っているため、「カビは裏まで侵食するけどカビ取り剤はしみこんでいかない」という状況が起こります。このままだと、表から対処不可能な壁紙の裏でカビが繁殖してしまい、より広範囲にカビの被害が広がる可能性が高いです。
そして、壁紙表面で発生したカビと違って壁紙裏で繁殖し表に出てきたカビというのは、再発や拡散のスピードが段違いに早いのです。早急に壁紙の張替えと除カビ防カビ処理をお勧めいたします。この時に注意してほしいのが、壁紙を取り換えるだけでは再発率が跳ね上がるということです。壁紙の裏までカビが侵食していた場合は、その壁紙が接触していた面(ボードやベニヤ)の除カビ防カビ処理をしないと、カビの種を閉じ込めることになるため、ほぼ確実に再発します。おすすめは壁紙はがす→ボードの除カビ防カビ→新しい壁紙を張る→壁紙を防カビの処理です。壁紙の中にカビ菌が残った場合と空気中から再付着する場合どちらの再発も防げます。
壁紙屋さんのほとんどが、カビに関する知識や経験が少ないために何の処置もせずに壁紙を貼ろうとしますが、指摘するようにしましょう。ここでもし仮に、壁紙のみではなく壁紙の裏のボードやベニヤ板にカビが侵食してしまった場合は、ボードやベニヤの張替えが必要になります。そうなるとより高額になってしまうため、壁紙を張り替え+ボードの除カビ防カビのみで済む今のうちにきちんと対処してしまった方が安く済むのです。
このようにならないためにも、壁紙にカビが発生しているのを発見したら、なるべく早期に市販のカビ取り剤やアルコールで対処する必要があるのです。
3-2.ボード壁
多くの場合は、ケイカルボードが使われていると思います。ケイカルボードは水に弱い建材です。何度も濡れた雑巾などで吹いていると、建材を痛めてしまう可能性があります。そのため、カビ取り剤でカビを除去しようとするならば、キッチンペーパーを使った湿布をお勧めします。
カビは石膏部分が大好物ですので、カビを除去した後しっかりと換気や湿度管理をしてください。
3-3.ペンキ塗りの壁
初期のカビであれば、市販のカビ取り剤をキッチンペーパーで湿布することで取れることが多いです。
しかし、除カビ剤のアルカリの成分により塗料を痛めてしまう場合があります。また、カビを放置してしまっていた場合、ペンキ部分が劣化してしまい、結果としてペンキを一度剥がし、除カビをしなければ、再発してしまう場合があります。
壁紙と同じく、ペンキが浮いていたり、ペンキの中もかびていると判断できる場合、業者に依頼することをお勧めします。
ここで最悪なケースは、カビの処置をせずに上から塗りつぶしてしまうことです。お客様の中には、カビたら塗ってを繰り返して、壁がカビと塗料のミルフィーユのようになっている現場もありました。
塗料の奥や塗料の中にカビが入り込んでいると、表面をいくら除カビ防カビしても壁紙の裏に繁殖した場合同様、再発率が格段に跳ね上がります。
本来は塗料をすべて溶かすか削るかしてからの処置が必要ですが、高額になってしまうので、せめて除カビ防カビ処理をしてから塗りなおしましょう。
3-4.珪藻土
珪藻土は、湿度を調整しカビを生えにくくするための建材です。
しかし、条件が揃うとカビが生える可能性があります。もっとも使ってはいけない場所は、壁が結露するような場所や湿度が高い場合です。
珪藻土は、ボードの上に珪藻土を塗る形なのですが、珪藻土の厚さは1ミリ程度です。
そのため、珪藻土の調湿能力では賄えず、結露をすべて珪藻土が吸い込んでしまい、常に湿った状態になり、カビが生えてしまいます。
さらにアルカリ性の珪藻土ならいいのですが、物によっては中性でカビが生えやすかったりします。
これからリフォームなどで珪藻土を使う場合は、使う環境や珪藻土の種類に注意が必要です。
珪藻土にカビが生えてしまった場合、非常に除カビが難しいです。おそらく市販のカビ取り剤では、除去が非常に難しいと思います。さらに、除カビ剤を塗布すると土なので水に弱く剥がれてしまいます。
通常施工する場合は、珪藻土を一度剥がし、再度珪藻土を塗りなおすか、防カビ仕様のクロスを貼りなおすのが一般的な方法となります。
3-5.コンクリート壁
コンクリートは基本的にアルカリ性でカビが生えづらいです。しかし、年数がたつとコンクリートのアルカリ性を保つ働きをする水酸化カルシウムが空気中の二酸化炭素と反応し、炭酸カルシウムになります。結果としてphが下がって、中性になりカビが生えやすい状態になってしまいます。
また、コンクリートの壁にカビが生える一番多い原因が結露です。コンクリートは熱伝導率が良く、熱容量も大きいために結露してしまうケースが多いです。
そうすると、常に壁面が濡れているといった状態になるため、黒カビ等が発生することが多いのです。
カビを除去する方法は、コンクリートですので水に強いため、部屋内ならキッチンペーパーを使用して除カビ剤を30分ほど湿布して放置し、水拭きを念入りにします。その後の防カビに関しては、結露が解決しないと根本的な解決にはならないのですが、結露防止シートなども正直効果は薄いため、こまめに拭いたり、室内の湿度を下げることで結露を抑えるなどの対策が必要になってしまいます。
3-6.外壁
外壁のカビは、ただカビ取り剤を塗布するだけでは効かないことがあります。
理由はカビ以外に油汚れ・酸化汚れが混合しているためです。
汚れにはカビ汚れ、酸化汚れ、油汚れの三種類から構成されており、それぞれ汚れを完璧に落としてからカビを除去する必要があります。
我々のようなカビ取り業者であれば、特殊な薬剤を使い、汚れを完璧に落としてからカビを除去することできます。しかし、一般の方には難しいので、高圧洗浄や水洗いで汚れを可能な限り除去してからカビ取り剤を塗布し、除去してください。
4.壁にカビを生やさないためのカビ対策
特殊な防カビ剤を用いずにお客様ご自身でカビを生やさないよう対策するためには、除湿機やエアコンを用いて湿度を60パーセント以下に保つ、結露が起こるところはこまめに拭くといった水分対策、空気が滞留しないように扇風機を回すといった風流対策、ほこりや汚れがたまらないように掃除を徹底するといった栄養対策などが有効です。
どれも完ぺきに行うのは非常に難しいですが、すべてを5割くらいの精度で複合的に行うだけでカビ発生の可能性は激減します。
そして、何度も言いますがカビは発生させないことよりも発生した後放置しないことが非常に重要です。カビ菌が目視できる状態というのは、「すでに胞子を飛ばして拡散しようとしている状態」を表します。繁殖が進んでしまうとお客様ご自身の手では対処不可能になってしまいますし、業者の施工費用も上がっていきます。
面倒くさがったり甘く見たりせずに、壁にカビが生えているのを見つけたらすぐに対処するようにしましょう。
5.壁のカビを除去する際の注意点
例えば、50cm×50cm程度の除カビをする場合、カビが生えている部分の周辺には、カビ菌が確実にあるため、最低でも周囲1m×1m、可能であれば部屋全体を除カビする必要があります。
カビが生えているところのみ除去してもすぐ再発してしまうため注意が必要です。
というのも、本来カビは基本的に無色透明ですが、十分成長して胞子を飛ばそうとするとカビに色がついていきます。そのため、カビが目に見える場合には空間全体にカビが胞子を飛ばしている可能性が高いのです。そのため、目視できるカビがある場合は一刻も早く対処する必要があります。
もしも部屋中にカビが広がっているかどうか気になる場合は、カビ菌のレベルをチェックすることができますので、心配であれば専門会社にチェックを依頼することをお勧めします。
お客様ご自身で対処される場合はカビの除去後も、業務用の防カビ剤を使わなくても周辺だけではなく部屋全体を一度除菌し、除湿を徹底すれば再発のリスクをかなり下げることができます。
6.業者に依頼する場合のポイント
業者に依頼する基準はそれぞれですが、いくつかポイントがありますのでご説明します。
(1)カビが転移している場合
カビがいたるところにできてしまった場合、確実にカビ菌が部屋全体についています。
この場合は部屋全体を除去しなければ、自分で除去してもまた再発してしまうリスクが高くなります。
お客様ご自身で対処してもよろしいですが、かなり大変な作業になるかと思います。
(2)壁紙や塗料の奥までカビが侵食していた時
この場合はお客様で解決することはほぼ不可能なので、きちんとカビの知識を持った業者に依頼するしかありません。間違っても壁紙を張りなおすだけ、塗料を重ねて塗りなおすだけといったことはしないようお勧めします。
(3)一度除去したけど再発した場合
数日で再発した場合、それは新しく生えたのではなくもともといたカビをきちんと除去出来ていないからです。再発すると、カビ菌にカビ取り剤の抗体が出来てしまうため、さらに強いカビになって生えてきてしまいます。そうなってしまうと市販のカビ取り剤では完全除去がどんどん難しくなってしまう場合があります。数日間で再発してしまった場合は必ず業者に依頼してください。
h2>7.リフォーム後の再発が意外に多い理由
一般的なリフォーム会社や清掃業者は、「カビの除去」に関しての専門業者ではないので、「カビ」に関して知識が乏しく、カビの完全除去をするのは大変難しいのが現実です。
壁紙リフォームしたのに1年も経たないうちにまたカビが生えてきた!ハウスクリーニング会社に依頼して壁を掃除してもらったけどカビがすぐに生えてきた!などといった依頼が非常に多くあります。
リフォーム会社の中には、リフォームの時に、ペンキや壁紙でカビを上から隠そうとしたり、お客様が使っているものと全く同じような一般的な市販のカビ取り剤で一時的に簡単にカビを取ろうとする業者もあります。
それらの業者はカビ対策において「菌を残す」ことの怖さを理解していないのです。カビ菌を少しでも残すと、残ったカビから菌糸を伸ばし、早い時期に表に出てくるようになります。その上から除カビをしても再発を繰り返し、建材を傷めてしまうため、最悪の場合、再度リフォームのやり直しが必要となり、費用も余計にかかってしまいます。
カビが生えたことで、リフォームをお考えの場合は、弊社のようにカビ取りとリフォームの両方をしている会社か、一度カビ取り業者を現地確認してもらい、適切なアドバイスをもらう事をお勧めします。
8.まとめ
一般家庭で簡単に除去できるカビは、小さいうちのカビに限ります。部屋のいたるところにカビが発生した場合や50cm四方以上の大きさの場合は、自分でカビの完全除去をする事は難しくなってくるので、専門業者に依頼した方が、結果的に費用対効果が高くなるケースがほとんどです。
発見したら市販のカビ取りでこまめに除去することで無駄なコストを削減出来ますし、カビによる健康被害も未然に防ぐことが出来ますので、カビ除去方法やカビ対策について、わからない場合はお気軽にお問い合わせください。