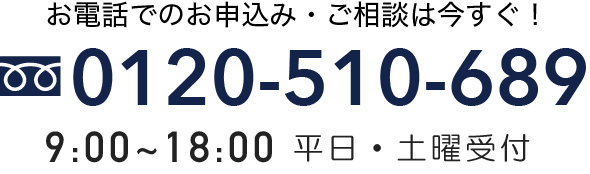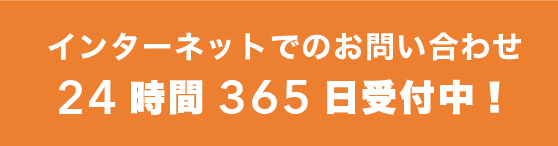カビによる死亡例!?癌・肺炎・喘息・・・本当に怖い放置されたカビ被害


みなさまは、カビが発生したのを見つけた時、すぐ対処されていますか?ほとんどの方は、多少のカビは放置し、カビがかなり目立ってから市販のカビ取り剤で除去されているようです。
実はカビを放置すると、健康被害も経済的な被害もかなり大きなものになるのです。ここでは、カビを放置したことによって、どのような被害が生じるのか理解していただき、ぜひご自身で正しい対処をしていただきたいと思います。
[toc]
1. カビってこんなにたくさんの種類がいるの!?
いきなりですが、みなさまは、地球上にどのくらいのカビが生息しているかご存じですか?カビは、実に6万〜7万種類と莫大な数が存在していると言われています。その中で、わたしたちが普段の生活で良く見かけるカビは、数種類に分けることができます。
■クラドスポリウム(Cladosporium)
通称:クロカビ
色:黒
室内外でみる黒いカビは、ほとんどがこれといってもいいくらいよく目にするカビです。空中に浮遊する最も多いカビで、喘息などを引き起こすことで知られています。
比較的水分の多いところで生えますので、風呂場、脱衣所、結露する窓や壁によく見られます。
湿度対策が一番有効な種類のカビです。
■セハロスポリウム(Cephalosporium)
色:白色〜赤系統色
洗面所や水回りによく現れるカビです。
■フザリウム (Fusarium)
通称:アカカビ
色:赤色
主に畑などに多く生息するカビの一種で、カビ毒により嘔吐・下痢などを引き起こす場合があります。浴室や水回りにも現れます。
■アスペルギルス (aspergillosis)
通称:コウジカビ
色:黄土色や黄緑色
自然界において最も多く見るカビの一種で、わたしたちの身近な生活環境のいたるところに生えています。
■アオカビ(Penicillium)
通称:アオカビ
色:緑色や黒色
パンやミカンなどに生える青カビでも知られており、わたしたちの身近な生活環境のいたるところに生えています。
■ユーロチウム(Eurotium)
通称:カワキコウジカビ
色:黄土色
乾燥したところ好むカビで、カメラなど精密機器に発生する場合があります。
2. カビってどこに生えるの?
わたしたちは普段の生活の中で、カビを良く見かけるのはどこでしょう?
キッチン、洗面所、お風呂などの水回りや窓のふちなどが多いですよね。これは、このあたりがカビが繁殖しやすい場所だからです。
では、具体的にカビはどんなところに生えやすいのか見ていきましょう。
2-1 酸素があるところ
カビは基本的に酸素のある環境でないと生えません。とはいえ酸素がないと私たちも生きていけないので、対策のしようがないですよね。
2-2 栄養源があるところ
カビは本当にいろいろなものを栄養源としています。ホコリ、食べかす、皮脂のような有機物だけではなく、ガラスやコンクリート、合金といったものまでも養分として食べ、増殖するのです。つまり空間どこでも、カビが生える可能性があるということです。
可能な限りホコリやゴミをためないことで防カビ対策にはなりますが、一度繁殖してしまったら栄養源を断つことはほぼ不可能です。
とにかくこまめな掃除と、カビが小さいうちに除去することが重要です。
2-3 温度が25度〜30度、湿度60%以上であること
カビは湿気を好みます。梅雨の時期は、冬の時期に比べてカビが繁殖しやすいですよね。これは温度と湿度がカビに最適な環境になるからです。
種類にもよるのですが、基本的には湿度を60%以下に保つことがカビをはやさないコツになります。(カワキコウジカビなど、低湿度のところに生える者もいます。)湿度は低ければ低いほどカビの発生確率は下がるのですが、30%を切ってしまうと今度は乾燥により感染症やのどの痛みなどのリスクが発生します。
カビが生えやすい箇所、カビが生えやすい部屋、カビが生えやすい建物、カビが生えやすい地域など、カビが局所的にたくさん生えるのは、ほとんどこの湿度が原因です。
2-4 そもそもカビ菌の数が多い
同じ湿度同じ栄養素の量の環境で、カビ菌の菌糸が壁面にたくさん生息しているところと、空気中に胞子が微量に存在するところでは、確実にカビ菌の多いところのほうが発生も被害の拡大も早いです。
ですので、確実な対策をしたい場合は徹底した除カビを最初にやることが大事です。
2-5 まとめ
まとめると、カビを生やさないためには「カビ菌を減らして湿度管理を徹底してこまめに掃除」につきます。防カビ剤でコーティングすればより完璧ですが、通常の環境であれば上記の対応を徹底的にやれば発生の可能性は低いでしょう。
次に、カビの被害について説明しますが、先に強調しておきたいのが「繁殖する前に対策するのが一番簡単で一番安い」です。繁殖してしまうとどうなるのかを次で見ていきましょう。
カビの被害
カビが繁殖してしまうとどのような被害が発生するのかを説明していきます。
まず、「一度放置して繁殖してしまったカビはなかなか手に負えない」このことを、よく覚えておいてください。
では実際にカビを発見したとき、そのまま放置してしまうとどうなるのでしょうか?カビの繁殖は実は目に見えないところで人間の健康にも大きな影響を与えています。ここでは、代表的な被害についてご紹介したいと思います。
3-1. 咳の被害
喘息、肺炎などの気管支に疾患のお持ちの方は、咳が止まらなくなることがあります。特にお子さまや高齢の方、風邪で免疫力が弱まってしまっている方は重い症状になる可能性があります。
一度肺炎で入院して退院後家に帰ってきたら、繁殖したカビのせいで家に住めなくなったという話は少なくありません。
肺や気管支が弱っている人にとっては、思い出あふれる自宅にもカビ菌生えてしまうともう住めなくなってしまいます。
カビとは、健康で幸せな生活を壊してしまう、恐ろしいものです。
3-2. 感染症
カビ菌というのは胞子を吸う分には普通の免疫を持つ一般の健康な方には問題ないのですが、病気などで免疫が低下してしまった方の場合、真菌症という病気に感染しやすくなります。皮膚に発生する疾患や、最悪の場合肺や呼吸器にカビが発生する疾患などが挙げられます。
まだ免疫力の弱い赤ちゃんのほっぺにカビが生えてしまうケースも実は割と多いのです。
健康的な免疫力があるうちは問題ないカビでも、免疫が弱っている状態で触れると一気に重大な被害になってしまいます。
3-3. カビ毒による食中毒
カビ毒による中毒症状は、カビが食品を汚染、堆積した毒素を体内に入れることで起こります。
同じ毒素でも
・急激に症状として表れる「急性毒性中毒」
・慢性的に接種し続けたことで緩やかに症状として表れる「慢性毒性中毒」
にわけられます。
代表的な例は、急性毒性中毒の場合は食中毒、慢性毒性中毒の場合はガンを発症させる危険性があるので注意が必要です。
よくある間違いとしては、カビ菌出すカビ毒は耐熱性があり、熱しても食中毒になってしまう恐れがあるので、かびてしまった食品は捨てるようにしましょう。
3-4. カビ自身がアレルゲンとなるアレルギー
アレルギーは、カビやその胞子を吸引して、免疫系が異物として排除しようとすることで起こる喘息やアレルギー性鼻炎(花粉症に近い)になる場合があります。
カビが皮膚に付着した場合は、アトピー性皮膚炎などの皮膚疾患を引き起こす可能性があります。皮膚が乾燥や虫刺されでもないのにかゆい症状がある場合、カビが原因とも考えられますこの症状に関しては、自分の身体に対するケアと、カビやほこりを周囲から減らす環境に対するケアと両方するのが効果的です。
3-5. カビを放置してしまうとどうなるか!?
健康的な人はあまり感じませんが、一度免疫が低下すると、以上のような重大な健康被害が発生する恐れがございます。
とにかく厄介なのは、放置してしまったカビは、市販のカビ取り剤ではもう完全には除去できないということ。壁ごと撤去したり、業者用の薬剤を使ったりしなければ、根本的な解決は不可能です。
そうならないためには、カビの特徴を理解し、放置せずに、しっかりと正しい早期対策を行うこと。それができれば、そんなに大変な思いをすることなく、カビ発生を抑えることができるのでご安心ください。
4. カビを抑える3つの対策
カビを発生させないためにはいくつかの方法があります。こちらをしっかり実践して、そもそもカビを発生させないようにしましょう。
4-1. 「掃除」
2-2でお話した通り、カビは栄養源があるところに発生します。こまめに掃除をして清潔感のある空間を作ることで、カビの繁殖を圧倒的に抑えることができます。
現場経験で学んだことより、ここだけは必ず掃除しておくべき場所をお伝えします!
■タンス、棚、テレビ台の裏側、部屋の四隅
タンスや棚の裏は、空気が滞留しやすくカビが生えやすい環境に加え、普段の掃除がしにくい部分、カビが生えやすい場所です。わたしたちがカビ取りの現地調査をする際、必ず見るチェックポイントの一つです。
・タンス
・棚
・テレビ台の裏側
・タンス・棚のボード
・部屋の天井・壁
・部屋の天井・壁の四隅
特に部屋の四隅は要注意です。
・汚れやすい
・掃除しずらい
・空気が滞留しやすい
・湿気がたまりやすい
という悪条件のため、普段なかなか手が行き届かない場所。小まめに掃除することをおススメします。
■お風呂場
お風呂場についても、部屋と全く同じく四隅やゴムパッキンなどが要注意です。
「掃除がしづらい=カビの絶好の住み家」
ですので、こちらも小まめに掃除することをおススメします。
4-2. 「除湿と換気」
カビが最も発生しやすい水回りやタンスの中には湿気が多く、それらを換気することによって除湿しましょう。一日に数回は窓をあけ換気したり、換気扇を回したりするだけでだいぶ違います。
最も効果的なのは、除湿器を設置することです。「どんな除湿器がいいですか?」といったご質問をいただくことがあるのですが、基本的にはどんな種類でもいいです。強いてもとめるなら湿度計がついた除湿器にしますと、管理がしやすいと思います。
カビが生えやすい湿度は65%以上です。それ以下に保つことができれば、カビの発生をかなり抑えることができます。除湿器がない方はぜひご購入を検討してみてください。
4-3. 「空気清浄機や光触媒コーティングの利用」
上記の二つを主に行い、さらに空気清浄機や光触媒の利用をすることでカビ胞子の不活性化や臭気物質の分解除去を行い効果的にカビの発生を防止できます。
4-4. カビを抑える効果的な方法
上記の3つを意識し、普段の生活から習慣化させることにより、年中発生してしまっていたカビを防止できます。
少しの努力で恐ろしい被害を防げるので、どうか楽観視して放置せず、早めの対策を心がけましょう。
5. まとめ
カビ毒には、発がん性があるものや喘息・肺炎などを引き起こすなど危険な場合があります。健康体の時であればそれほど感染するリスクは高くないのですが、少し体調が悪い時や疲れがたまっている時、寝不足の時など免疫力が下がっている時に感染しやすくなります。
まだ体力もない子供や高齢の方が感染すると非常に重篤な症状に発展することもありますので、小まめに湿度管理、掃除を行い日頃からカビ対策をすることをおススメします。
現在カビでお困りの方
当社では、御見積(関東圏・沖縄県)は無料で行っております。カビでお困りの際は、カビ対策専門会社である当社までお気軽にご相談ください。